冬の暖房、何を選ぶかって本当に悩みますよね。
「足元が寒い」「部屋全体が暖まらない」「電気代が高すぎる」――そんな声、我が家でも毎年出ます。
特に4LDKのような広めの間取りだと、どこをどう暖めるかで快適さも電気代も大きく変わるんです。
そこで今回は、主婦目線で気になる2つの暖房スタイルを徹底比較してみました。
- 【①床暖房】LDK+各居室に温水式床暖房を導入(計40畳)
- 【②エアコン5台+LDKにこたつ&ホットカーペット】各部屋にエアコン、LDKは3種併用
それぞれの導入費・光熱費・メンテナンス費・暮らしやすさを、リアルな数字と生活感で見ていきましょう。
【コスパいいのはどっち?】床暖房VSエアコン+こたつ+ホットカーペット
| 床暖房 | エアコン+こたつ+ホットカーペット | |
|---|---|---|
| 導入費 | 1畳あたり:約5万〜10万円 LDK(20畳)+主寝室(8畳)+子ども部屋2室(6畳×2)+和室(6畳)=計46畳 合計:約230万〜460万円(熱源機含む) | エアコン(6畳×4台+20畳用1台):約60万〜80万円 こたつ(省エネモデル):約1.5万円 ホットカーペット(3畳用):約2万円 合計:約63.5万〜83.5万円 |
| 光熱費 | 1畳あたり:約4〜6円/時 46畳×5円×8時間×30日=月55,200円前後 | エアコン(5台):約52円/時×8時間×30日=月12,480円前後 こたつ:約4円/時×8時間×30日=月960円 ホットカーペット:約8円/時×8時間×30日=月1,920円 合計:約15,360円前後 |
| メンテナンス費 | 熱源機の交換(15〜20年):約30万〜50万円 配管の点検・修繕(20年目以降):約10万〜30万円 年間点検費:1万〜2万円(任意) | エアコン:フィルター掃除(月1回)、プロクリーニング(2〜3年ごと)1台約1万〜1.5万円 こたつ:ヒーター交換(5〜10年)約3,000〜5,000円 ホットカーペット:寿命5〜8年、故障時は買い替え(約2万円) |
コスト比較としては圧倒的に【エアコン+こたつ+ホットカーペット】の勝利!!!
床暖房の1/4~1/6くらいまで節約できます。
導入費、メンテナンス費がどうしても床暖房は高くなります。
ただし、電気代については太陽光パネルの設置などで対策可能ですね。
【暮らしやすいのはどっち?】床暖房VSエアコン+こたつ+ホットカーペット
| 床暖房 | エアコン+こたつ+ホットカーペット | |
|---|---|---|
| 快適さ | LDK全体がじんわり暖かく、どこに座っても快適 | 動線が偏り、こたつから離れた場所は寒く感じることも |
| 足元から暖まるので、子どもが床で遊んでも安心 | こたつ周辺だけが暖かく、家族がそこに集中しがち | |
| すぐにあたたまる? | 立ち上がりに時間がかかるため、急な寒さには不向き | エアコンは、立ち上がりが早く、すぐ暖まる こたつ&ホットカーペットは足元がすぐ暖まり、家族が集まりやすい |
| 乾燥 | 足元から均一に暖まり、空気が乾燥しにくく、喉や肌への負担が少ない | 空気が乾燥しやすく、加湿器併用が必要 |
| 掃除のしやすさ | 掃除機・ロボット掃除機がスムーズ(器具が出ていない) | こたつ周辺に物が集まり、掃除がしづらくなる ホットカーペットの下にホコリが溜まりやすい |
| 安全性 | ヒーターやコードがないため、小さな子どもにも安全 | コードやヒーター部分に子どもが触れるリスクあり |
| 注意点 | 床材の選定によっては傷や汚れが目立ちやすい | 寝落ち・動かなくなるリスクあり(快適すぎて) |
快適さ・安全性・掃除のしやすさでは床暖房が優位。
子育て世帯にとっては床暖房のほうが安心感がありますね。
ただし、こたつの“ぬくもり”は家族の絆を深める場にもなるので捨てがたいかも。
快適さとコストの“ちょうどいい”バランスを探して
私たち家族も、床暖房に憧れた時期がありました。
「足元から暖かいって最高じゃない?」
「乾燥しないって、子どもにもいいよね」
そんな気持ち、すごくわかります。
でも、見積もりを取ってみると…
- 初期費用が200万〜400万円
- 光熱費が月5万円以上になる可能性
- メンテナンス費も将来的に数十万円単位
一方で、エアコン+こたつ+ホットカーペットの組み合わせなら
- 初期費用は約60万〜80万円
- 光熱費は月1.5万円前後
- メンテナンスは分散していて、計画しやすい
もちろん、快適さでは床暖房が圧倒的。
でも、今の生活コスト・将来の教育費・家族の動きやすさを考えると、
「併用スタイルの方が“ちょうどいい”かも」と感じました。
暖房選びは“暮らし方”で決めていい
床暖房も、エアコン+こたつ+ホットカーペットも、どちらも素晴らしい選択肢です。
でも、どちらが正解かは、家族の暮らし方によって違う。
- 快適さを最優先するなら床暖房
- コストと柔軟性を重視するなら併用スタイル
家族の未来を見据えて、「今の暮らしに無理がないこと」「将来の変化に対応できること」
そんな視点で選ぶことが、いちばんの安心につながると思います。
暖房器具だけでなく、窓ガラスやサッシ、壁や床の断熱性能によっても快適さって変わってくるんですよね。
次回の記事では、そのあたりも深堀していこうと思います。
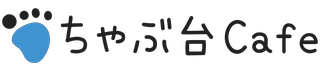

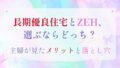
コメント