「家を建てたい」と思ったとき、まず考えるのは間取りや外観、設備のこと。
でも実際に動き始めると、最初にぶつかるのは「土地がない」という現実でした。
建売住宅なら土地込みで販売されているので、土地探しの手間はありません。
でも、注文住宅を考えるなら、まずは土地を見つけなければ始まりません。
そしてこの“土地探し”が、想像以上に難しく、落とし穴だらけなんですよね。
落とし穴①|そもそも土地が出てこない
希望エリアで土地を探してみると、驚くほど情報が少ない。
「駅徒歩圏」「学区内」「治安が良い」「災害リスクが低い」など、条件を絞るほどに、候補はほぼゼロに近づいていきます。
出てきたとしても、価格が高すぎるか、形状が悪いか、災害リスクがあるか。
「土地はあるけど、建てたい家が建てられない」
「価格は安いけど、通学に不便」
そんなジレンマに何度も直面しています。
落とし穴②|旗竿地の罠と、夫の実家での苦い経験
比較的価格が安く、情報として出てきやすいのが「旗竿地」。
道路から細い通路を通って奥に広がる土地で、見た目は“旗”のような形をしています。
一見すると「奥まっていて静か」「価格が安い」といったメリットがありますが、実際には注意点がたくさんあります。
- 日当たりが悪くなりがち
- 通風・換気が弱くなる
- 建築制限がある場合も
- 資産価値が下がりやすい
そして、私たちにはこの旗竿地にまつわる“実体験”があります。
それは、夫の実家が旗竿地だったということ。
駅徒歩5分という好立地。
通学にも通勤にも便利で、資産価値も高い。
「ここをリフォームして住めたら、土地代もかからないし、最高じゃない?」
そんな希望を持って、実際にリフォームの見積もりを取ってみました。
でも、現実は厳しかった。
まず、築60年という年数の壁。
耐震基準が現在のものとは大きく異なり、どう頑張っても構造的な不安が残る。
補強工事を入れると、費用は一気に跳ね上がります。
さらに、旗竿地という地形のハードル。
資材の運搬がしづらく、重機も入れない。
駐車場がないため、大通りにトラックを停めて作業する必要があり、
そのためには道路使用許可の申請や、交通整理の人員配置など、想像以上の手間とコストがかかることがわかりました。
最終的に出てきた見積もりは、新築を購入するのと同じくらい。。。。
しかも、リフォーム後も旗竿地の不便さは残る。
「それなら、土地も建物も新しくして、暮らしやすい場所を選んだ方がいいのでは…」
そう考えざるを得ませんでした。
泣く泣く、夫の実家リフォームの選択肢は諦めました。
そしてその経験から、私は「もう旗竿地は選ばない」と心に決めたのです。
価格が安く見えても、見えないコストが積み重なる。
それが旗竿地の怖さだと、身をもって知りました。
落とし穴③|災害区域の見極め方
土地情報を見ていると、「土砂災害警戒区域」「浸水想定区域」などの表記が出てくることがあります。
一見すると「避けた方がいい」と思いがちですが、実は都市部でも意外と多くの土地がこうした区域に含まれています。
土砂災害警戒区域とは?
- イエローゾーン:土砂災害の恐れがあるが、建築制限はなし
- レッドゾーン:特別警戒区域。建築に制限がかかる場合あり
【参考】全国の住宅地の一部は、警戒区域に指定されていても普通に住宅が建っています。
見極めポイント
- ハザードマップだけでは不十分
- 過去の災害履歴を調べる
- 地盤調査の結果を確認する
災害区域だからといって「絶対にダメ」とは限りません。
でも、リスクを正しく理解し、保険や避難計画まで含めて判断することが大切です。
またハザードマップは頻繁に更新されます。
実家に置いてあったハザードマップで大丈夫であっても、最新のハザードマップでは危険区域になっていたりとかなり変化があるので必ずチェックしています。
落とし穴④|価格の罠
土地の価格は、面積や立地だけで決まるわけではありません。
形状、接道、地盤、災害リスク、周辺環境など、さまざまな要素が絡んでいます。
例えば、同じエリアでも「整形地(四角形)」と「変形地」では価格が大きく違います。
また、接道が私道か公道か、幅員が何メートルかによっても、建築可能な建物の規模が変わってきます。
さらに、価格が安い土地には「理由」があることが多いです。
- 旗竿地
- 災害区域
- 地盤が弱い
- 周囲に嫌悪施設(工場、墓地、騒音源など)がある
「安いからラッキー」ではなく、「なぜ安いのか」を冷静に見極めることが必要です。
落とし穴⑤|土地と建物のバランス
土地を見つけても、そこに希望の家が建てられるとは限りません。
建築条件付きの土地だったり、建ぺい率・容積率の制限が厳しかったりすると、思ったより小さな家しか建てられないこともあります。
また、土地の形状によっては、間取りの自由度が下がることも。
「南向きリビングが取れない」「駐車場が狭くなる」「収納が減る」など、暮らしに影響する部分が出てきます。
家づくりは、土地と建物の“セット”で考えることが大切。
「土地が良ければ家も良くなる」とは限らないし、逆に「家が理想でも土地が悪ければ暮らしにくい」こともある。
そのバランスを見極めるのが、家づくりの難しさでもあり、面白さでもあると感じています。
土地探しは“暮らしの土台”を選ぶこと
土地探しは、家づくりのスタート地点。
でも、価格や立地だけで決めてしまうと、後悔することもある。
旗竿地、災害区域、地盤の弱さ、建築制限…見えづらい落とし穴がたくさんあります。
そして私たち自身も、夫の実家という旗竿地でのリフォームを断念した経験があります。
駅徒歩5分という好立地だったにもかかわらず、築60年の耐震不安、資材搬入の困難さ、交通整理の人員配置など、見えないコストが積み重なり、新築と同じくらいの見積もりになってしまいました。
その経験から、私は「もう旗竿地は選ばない」と心に決めています。
だからこそ、「何を優先して、何を妥協するか」を家族でしっかり話し合うことが大切。
そして、土地と建物のバランスを考えながら、現実的で納得できる選択肢を探していく。
それが、私たちの“ちょうどいい家づくり”につながるのかなと思います。
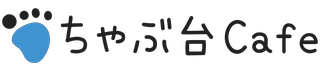
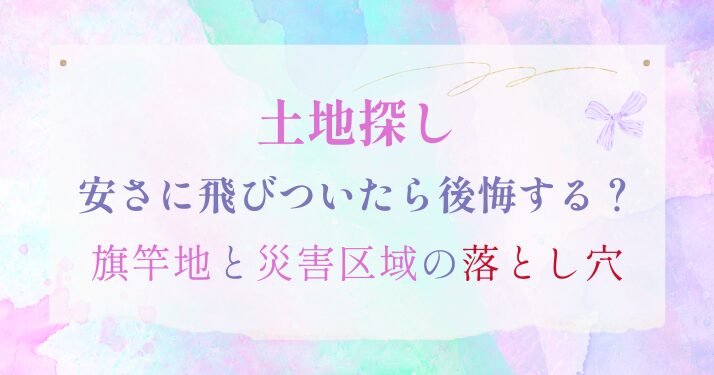

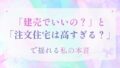
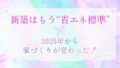
コメント