家づくりを考え始めて、住宅展示場やネットの情報でよく目にしたのが「長期優良住宅」という言葉。
「国が認めた高性能住宅」「補助金が出る」「税金が安くなる」――そんなふうに書かれていて、
「へぇ、なんか良さそうじゃない?」と、正直ちょっとワクワクしました。
でも、調べれば調べるほど、「あれ?これって本当にお得なの?」と疑問が湧いてきたんです。
特に気になったのが、“維持保全計画”という名のメンテナンス義務。
「補助金をもらう代わりに、ずっとお金と手間がかかるってこと?」
そんな不安が、じわじわと大きくなっていきました。
そもそも「長期優良住宅」ってどんな家?
ざっくり言うと、長期優良住宅とは、「長く、安心して、快適に住み続けられる家」のこと。
国が定めた基準をクリアして、自治体から認定を受けた住宅だけが名乗れる“優等生”です。
認定に必要な主な条件
- 耐震性:震度6強〜7の地震でも倒壊しない構造
- 劣化対策:数世代にわたって使える素材や工法
- 省エネ性能:断熱・気密性が高く、光熱費が抑えられる
- 維持管理のしやすさ:配管や設備の交換がしやすい設計
- 居住環境への配慮:周辺環境と調和した設計
- 一定以上の広さ:狭すぎない、ゆとりある住空間
- 維持保全計画の提出:点検・修繕のスケジュールを事前に提出
つまり、「ちゃんとした家を建てて、ちゃんと手入れして、ちゃんと住み続けてね」というのが、この制度の基本スタンス。
長期優良住宅の魅力的なメリット
- 住宅ローン控除の上限アップ(認定住宅は最大5,000万円まで)
- 固定資産税の減額(5年間)
- 不動産取得税の軽減
- 地震保険料の割引
- 中古住宅として売却する際の評価が高い
- 補助金の対象になりやすい
「どうせ建てるなら、少しでも得したい」
「将来売ることも考えると、資産価値が高い方がいい」
そんなふうに思うのは、当然のこと。
でも、ここで見落としがちなのが、“維持するためのコストと手間”なんです。
維持保全計画って、つまり“ずっとメンテナンスしてね”ってこと
長期優良住宅は、認定を受けたら終わりではありません。
むしろ、そこからがスタート。
認定を受けるには、「維持保全計画」という書類を提出する必要があります。
これは、今後30年〜60年にわたって、どのタイミングでどんな点検や修繕をするかをあらかじめ決めておく計画書です。
点検・メンテナンスの主な内容
- 構造躯体の点検(柱・梁・基礎など)
- 雨水の浸入防止(屋根・外壁・窓まわり)
- 給排水設備の点検・交換(配管・トイレ・キッチン)
- シロアリ対策の再処理(5〜10年ごと)
- 外壁塗装・防水処理(15〜20年ごと)
これらを定期的に実施し、その記録を残すことが義務らしい。
メンテナンス費用ってどれくらいかかるの?
正直、ここが一番気になるところ!!
実際の費用は、住宅の規模や仕様、依頼する業者によって異なりますが、ざっくりとした目安は以下の通りです。
| メンテナンス項目 | 頻度 | 費用目安(1回あたり) |
|---|---|---|
| シロアリ再処理 | 5〜10年ごと | 約10万〜15万円 |
| 屋根・外壁点検 | 10年ごと | 約5万〜10万円 |
| 外壁塗装・防水 | 15〜20年ごと | 約80万〜150万円 |
| 給排水設備交換 | 20年ごと | 約30万〜50万円 |
| 定期点検(業者依頼) | 5年ごと | 約3万〜5万円 |
これを30年スパンでざっくり合計すると、300万〜500万円程度になることも珍しくありません。
メンテナンス、やらなかったらどうなるの?
「点検って、やらなかったらダメなの?」
「記録って、誰に見せるの?」
そんな疑問も出てきますよね。
実は、自治体によっては点検記録の提出を求められることもあり、怠ると認定が取り消される可能性もあるんです・・・!!!
さらに、認定が取り消されると・・・
- 将来的に売却するときに「長期優良住宅」として評価されない
- 補助金や税制優遇の対象外になる
- 住宅ローン控除の条件に影響することも
つまり、「認定を受けたら終わり」ではなく、“維持する責任”がずっと続くということなんです。
ハウスメーカーによって“維持費の現実”はこんなに違う
ここ、ほんっとうに重要なポイントです!!!
「長期優良住宅って、どこで建てても同じでしょ?」と思いがちですが、実はハウスメーカーによって“維持費の現実”がまったく違うんです。
たとえば、
- A社は「60年長期保証!」とうたっているけど、実は10年ごとに有償メンテナンスを受けないと保証が切れる
- B社は「定期点検無料!」だけど、修繕はすべて有償で、部品代+工賃が高額
- C社は「維持費込みの定額プランあり」だけど、月額で積み立てると30年で100万円超え
つまり、“長期優良住宅”というラベルは同じでも、中身は全然違うんです。
だからこそ、「どの会社で建てるか」「どんな保証内容か」を、契約前にしっかり確認することが大切。
「長期優良住宅=正解」じゃなくていい
ここで声を大にして言いたいのは、
「長期優良住宅を選ばなかったからって、間違いじゃない」ということ。
制度としては素晴らしいし、合う人には本当に価値がある。
でも、私のように
- 子育て中で、今の生活コストを抑えたい
- 将来的に住み替えや売却も視野に入れている
- メンテナンスの手間や費用をなるべく減らしたい
という価値観を持っているなら、他の選択肢の方が“ちょうどいい”可能性もある。
たとえば、
- ZEH仕様のローコスト住宅:光熱費が抑えられて、補助金もあり
- 建売住宅+性能確認:省エネ基準を満たしていれば、暮らしやすさも十分
- 規格住宅+必要な部分だけグレードアップ:コストと性能のバランスが取りやすい
じゃあ、どうやって判断すればいいの?
迷ったときは、「30年後の自分たちがどう暮らしていたいか」を想像してみましょう。
- ずっと同じ家に住み続けたい?
- 子どもたちが巣立ったら住み替えたい?
- 将来的に売却や賃貸も視野に入れてる?
- そのとき、家にどれくらいの価値が残っていてほしい?
この“未来の暮らし方”によって、長期優良住宅が合うかどうかが変わってきます。
「長期優良住宅にしないと損」って思い込んでいませんか?
住宅展示場や営業トークでは、
「長期優良住宅は今や当たり前ですよ」
「将来売るときに有利です」
「補助金も出ますし、税金も安くなります」
といった言葉をよく聞きます。
でも、それって本当に“自分たちにとっての得”なんでしょうか?
- 補助金や減税で得られる金額は、数十万円〜最大で100万円前後
- 一方で、認定取得や維持にかかる費用は、数十万〜数百万円に及ぶことも
つまり、「制度上の得」と「家計的な得」は必ずしも一致しないんです。
制度に合わせるより、暮らしに合わせる
我が家は、「制度に家を合わせるより、暮らしに家を合わせよう」と思います。
もちろん、長期優良住宅のような制度を知っておくことは大切。
でも、それに振り回されて「本当は望んでいない間取り」や「無理な予算配分」になってしまったら、本末転倒ですよね。
我が家は、現時点で以下のような基準で家づくりを進めることにしました。
- 今の生活に無理がないこと
- 子どもたちの成長に合わせて柔軟に対応できること
- 将来のメンテナンス費用も見越して、貯蓄や教育費とバランスを取ること
- 「制度のため」ではなく、「家族のため」に選ぶこと
家づくりは「制度」より「暮らし方」で選ぶ時代へ
長期優良住宅は、たしかに魅力的な制度です。
でも、それは「“暮らし方が合っている人”にとっての魅力」であって、
すべての人にとっての“正解”ではありません。
家族の今と未来を見据えて、
「何にお金をかけるか」「どこに手間をかけるか」を冷静に考えている人にとっては、
制度に振り回されず、自分たちの価値観で選ぶことこそが、いちばんの安心になると思います。
家づくりは、補助金や認定を取ることが目的じゃない。
家族が心地よく、無理なく、笑顔で暮らせる場所をつくること。
そのために、「制度を使うかどうか」も、自分たちで選んでいいんです。
じっくり「自分たちに合う家ってどんなかな」を考えていきましょう。
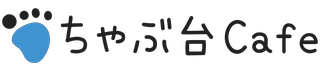
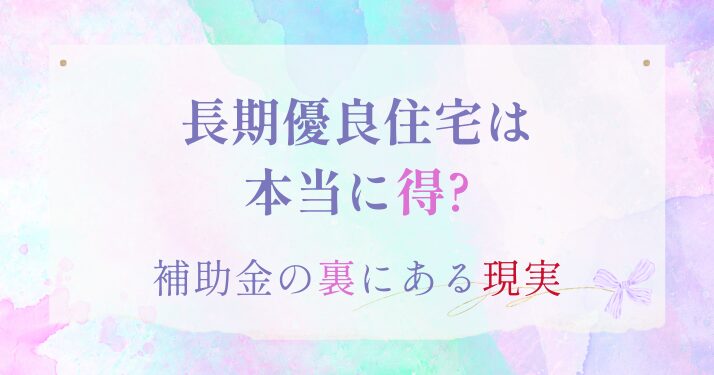

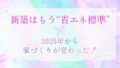
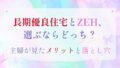
コメント